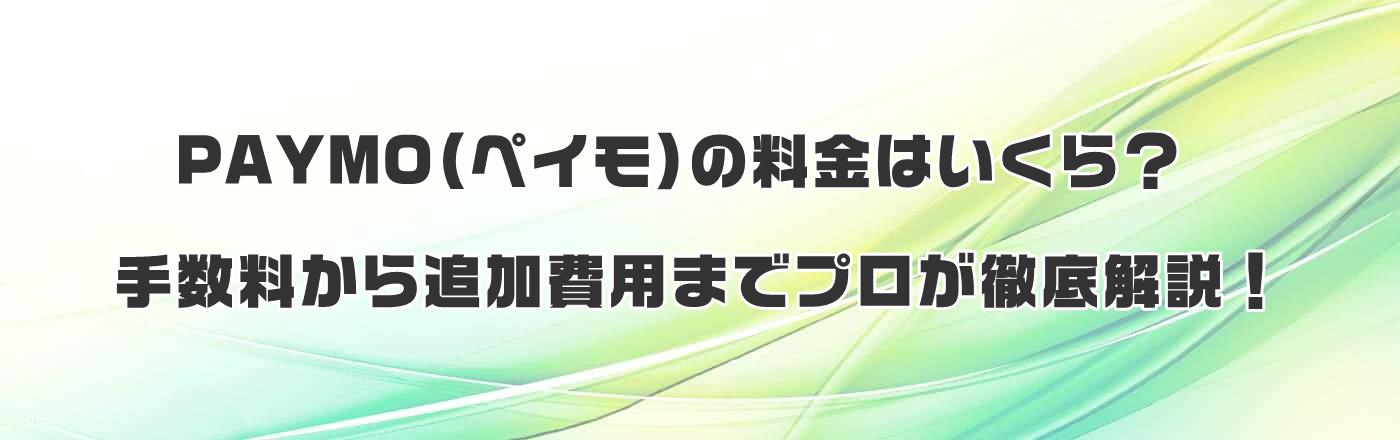
PAYMO(ペイモ)の料金はいくら?手数料から追加費用までプロが徹底解説!
PAYMO(ペイモ)の料金はいくら?手数料から追加費用までプロが徹底解説!
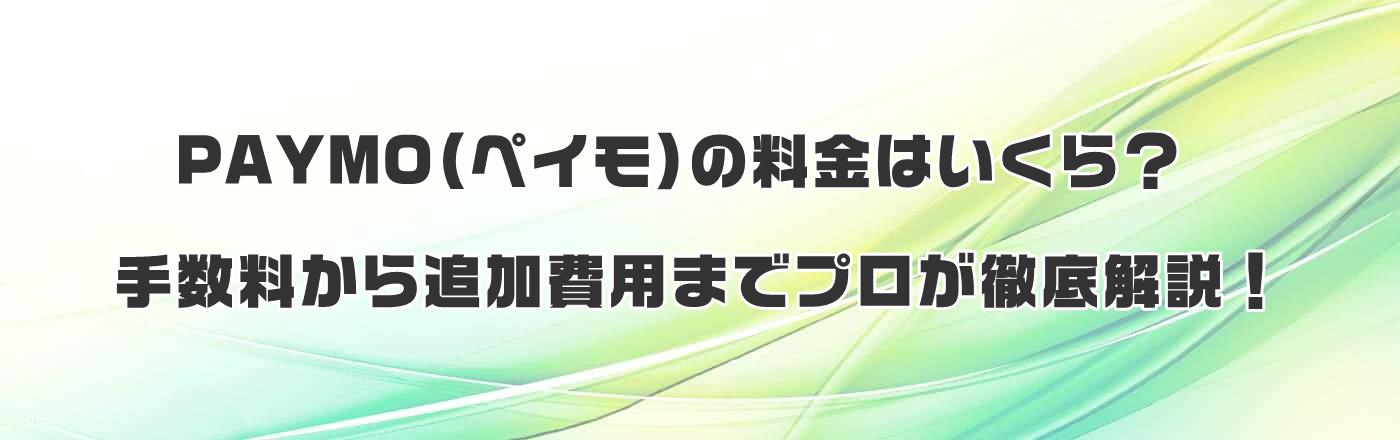
ーこのページにはPRリンクが含まれています。ー
この記事では、
「PAYMO(ペイモ)の料金はいくらなの?」
「料金以外でどのような費用が必要になるの?」
「追加で費用がかかる場合はあるの?」
といったことが知りたい方におすすめです。

結論:PAYMOの費用は「契約企業のプラン」と「振込手数料500円」で決まる
PAYMOを利用する際にかかる費用は、主に2つの要素で決まります。
直接払い型プラン(1%): あなたの契約先企業がPAYMOに前払い資金を預けている場合。手数料は申請額の1%と非常に安価です。
立替払い型プラン(3%〜10%): PAYMOが報酬を立て替える場合。手数料は3%〜10%となり、企業の信用力によって変動します。
サービス利用料とは別に、申請1回ごとに500円の振込手数料がかかります。
追加費用は原則かかりません。 万が一、契約先企業が倒産した場合でも、利用者が直接請求される可能性は極めて低いです。
「料金以外でどのような費用が必要?」「追加費用はある?」と検索する人へ
PAYMOの料金以外に必要な費用は、申請1回ごとに一律500円の振込手数料のみです。サービス利用料(手数料1%〜10%)に加えてこの固定費用がかかります。特に少額を頻繁に申請すると割高になるのでご注意ください。
追加費用が後から請求されることは基本的にありません。 契約先企業が倒産するなどの不測の事態が起きても、その損失を利用者が負うことは通常ない「ノンリコース」という契約形態が一般的だからです。安心して利用できる仕組みになっています。



| 申請金額 | プラン種別 | サービス利用料 | 振込手数料 | 合計費用 | 最終受取額 | 実質費用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000円 | 直接払い型 (1%) | 300円 | 500円 | 800円 | 29,200円 | 2.67% |
| 30,000円 | 立替払い型 (10%) | 3,000円 | 500円 | 3,500円 | 26,500円 | 11.67% |
| 100,000円 | 直接払い型 (1%) | 1,000円 | 500円 | 1,500円 | 98,500円 | 1.50% |
| 100,000円 | 立替払い型 (10%) | 10,000円 | 500円 | 10,500円 | 89,500円 | 10.50% |
| サービス名 | サービス利用料率 | 固定手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| PAYMO (直接払い) | 1% | 500円 | 導入企業次第だが、市場最安水準。 |
| PAYMO (立替払い) | 3%〜10% | 500円 | 一般的な2社間ファクタリングと同等か、やや有利な水準。 |
| labol (ラボル) | 一律10% | なし | 料金が分かりやすく、個人が直接契約可能。 |
| Paytner (ペイトナー) | 一律10% | 記載なし | labol同様、シンプルで分かりやすい料金体系。 |
| FREENANCE | 3%〜10% | なし | 利用実績に応じて手数料が下がっていく仕組み。 |

